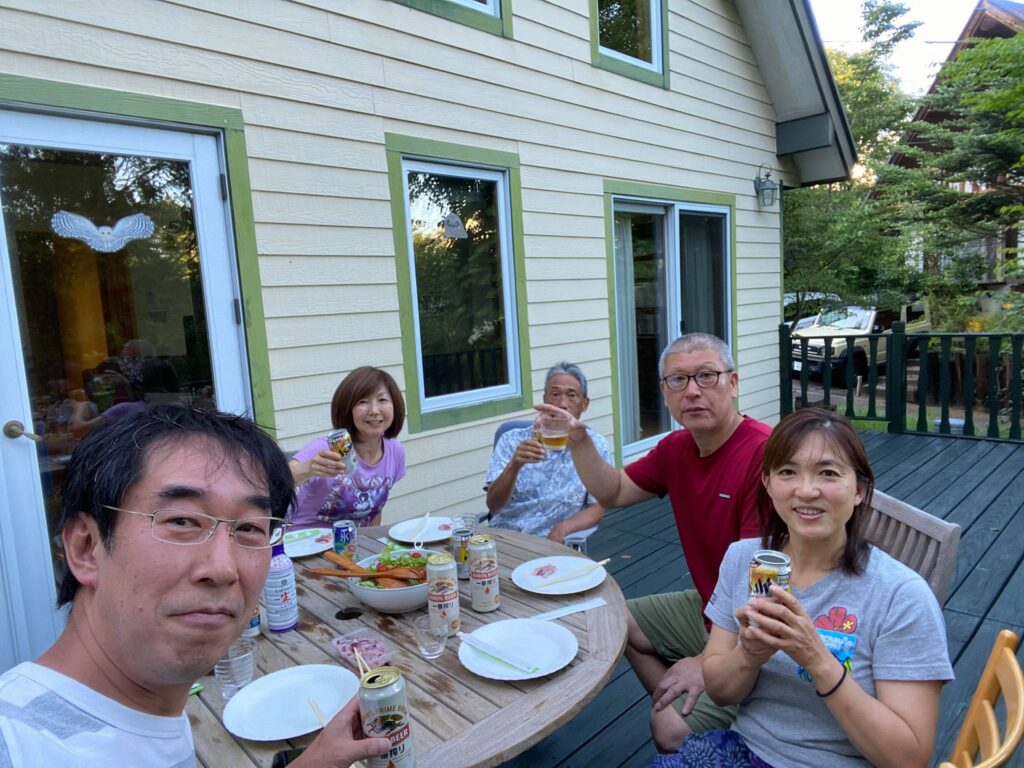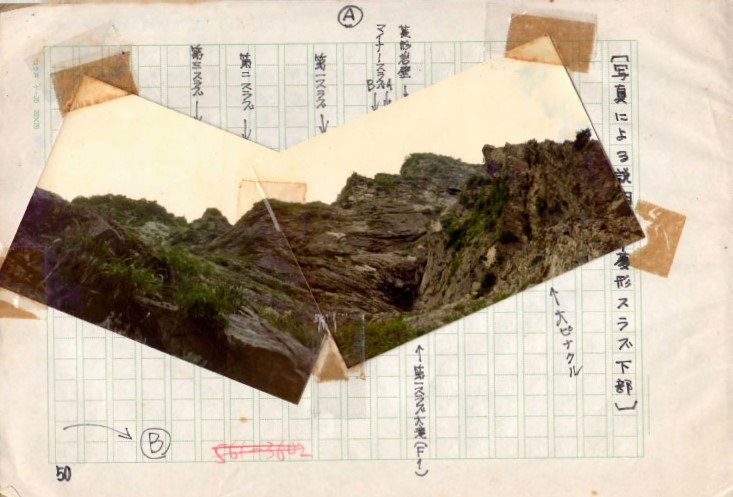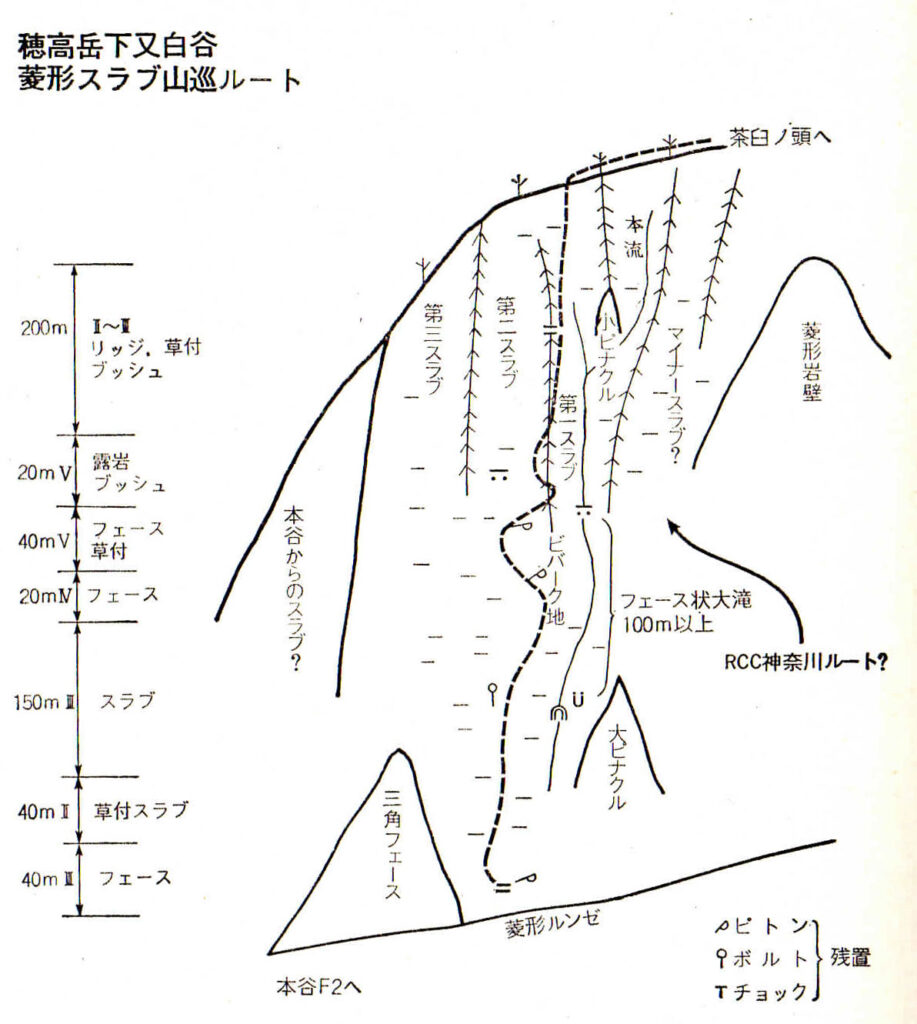源太ヶ城(跡)は、比志津金山塊のはずれ、大門ダムのすぐ東南の山城。
甲斐源氏ゆかりの黒源太清光が築城し、武田時代に活躍した津金衆が本拠としていたらしい。
武田信玄の狼煙台のひとつがここにあったという。

この林道、大門ダムのすぐ南から始まって源太ヶ城の南をぐるっとまわって東から北に巻き込んで山頂直下の二の丸(?)あたりに至る約2キロの道。幅は6メートル程度らしいが、すでに廃道となって倒木やら草に覆われている。もっとも登山道としては申し分のない快適な道。
大門ダムからのスタート地点は法面保護の擁壁が作られていて、道が寸断されている。
つまりこの林道には入口がない。
そもそもなんでこんな道が作られたのか。しかもなぜ自衛隊なのか。
途上にあった自衛隊顕彰碑やら、共有地記念碑なるものにあった記述を参照すると経緯は以下のようになる。
山梨県が、入会地であったこの山の入会地の譲渡を受け、県有地とする。
そのうえで1973年、須玉町長が自衛隊に依頼し、道を作ってもらった。
山城による観光振興を狙ったのか、それとも国防上の深淵なる作戦なのか。まあ実際のところ観光狙って失敗したってところなんでしょうが、山頂付近にはまるでロケット砲(花火?)の土台みたいなものがいくつもあったりして、後者と考えたほうがなにかと楽しいですな。
さてウッドペッカーキャンプ場から自衛隊の道に合流したあとは、林道を行かず山腹に直接とりつき、まっすぐに山頂を目指す。







2キロの林道をすべて歩いたが、入口のない林道なので、ウッドペッカーキャンプ場への道の分岐までまた戻り、下山した。
帰路、擁壁のあたりをよく見たら、草付きの林道あとのようなものがジグザグに伸びており、ここから林道入口に歩いて行けるかもしれない。