すっかり山にはまってしまった妻とのほぼ月一回ペースの山歩き。
私が妻の要望を聞きながら最適な山を探すスタイルから、最近は妻が勝手にリサーチして山を決めてくるスタイルになってきた。
今月のお題は「月山」。
6月に行った秋田駒ヶ岳が楽しかったせいかまた、東北の高山植物で有名な山シリーズ。
前夜7時間ほどのドライブで登山口へ行って車中泊。月山8合目登山口への県道は冬期閉鎖から開通したばかりだった。朝から登って温泉宿でのんびり休んでから帰るというパターンも定着してきた感じ。
直前に登った人のブログによれば、登山道に雪は残っているがアイゼンはいらないらしい。

午前中の天気がよさそうなので早めに出発。
平日の朝早くから駐車場はなんか騒然としていて、おそろいのヘルメットに沢装備?っぽい体格のよいお兄さんたちのグループがいるかと思えば、白装束の山伏姿の団体もいるぞ。そして警察官が寄ってきて「ここで行方不明になっている人がいるので、情報があったら連絡してください。」と遭難者の特徴なんかの書かれたチラシを受け取った。それはそれはご苦労様。ほんと頭が下がるわ。
つまりヘルメットのグループは警察の捜索隊だったわけですな。
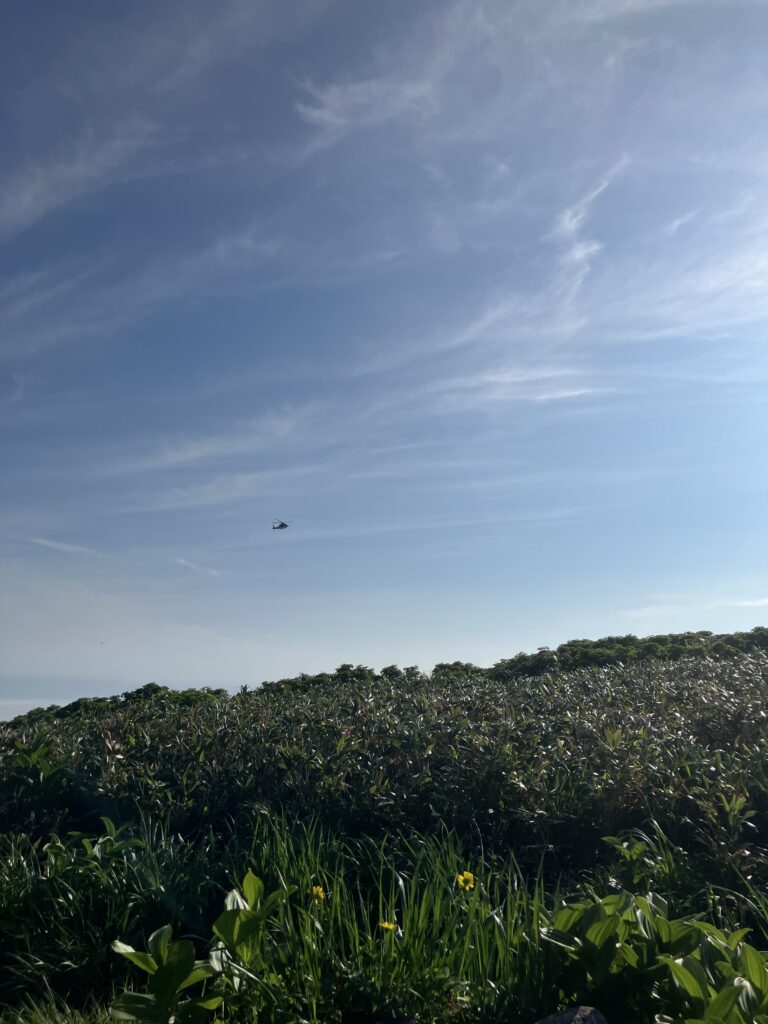
県警のヘリも午前中ずっと飛び回っていたけどこの日は見つからなかったらしい。



さすがに百名山。道もよく整備されてるね。

標高があがるとそこかしこに雪が残っているが、登山道は大した雪斜面もなく、運動靴で十分歩けるレベル。

高山植物はまさに花盛り。
高山植物初心者のわれわれは事前に「月山でこの時期に見られる花」の写真を集めて、花名とともにプリントして行ったのだが、そのプリントを車に忘れるといういつものやつ。

佛生小屋を過ぎると少し急なところもでてくる。


山頂手前はしばらく雪の上を歩くようになる。

雪の上を行くと、いつの間にか月山頂上への分岐を通りこし、月山神社をまわりこむようにして月山頂上小屋に来てしまった。
月山神社は500円払ってお祓いを受けないと立ち入りできないんだそうで、面倒なのでパス。てか駐車場で会った山伏姿の一行が大勢ここにいて混雑してそうだったのもあったし・・・。





というわけで往路を下山後、湯田川温泉で打ち上げして帰ったわけですが。
ちょっと山伏のお話。
山頂まで前方を件の山伏装束の人々が歩いていて、月山神社でもわらわらしていて、そしてわれわれがランチを終えて通りかかると、彼らは月山小屋でお弁当タイム。
それを外から覗き込んだ妻が「ほぼ全員欧米人よっ!」って。
「そういえばほら貝下手くそだったよね~。」と私。
道中もそのほら貝を聴きながら、「横に行ってパオーンとか叫んだらこっちのが本物ぽく聞こえるかも。」なんて軽くディスりつつ。
この人たちってどんな動機でこんなことしているんだろう?
誰がそういうツアー?を企画してるんだろう?
そもそも本気で修業したいのか、ただ観光的に体験してるだけなのか?
いろいろ気になったんで、帰宅してからGeminiさん(GoogleのAI機能)と相談。ネット情報を網羅的に調べてもらった。最大公約数的な二次的情報をとることに関してはAIってきわめて優秀ですな。
まず山伏とはなんだったのか?から始めてみよう。
質問「中世の山伏の実態について調べてちょうだい」
Deep Researchかけたら報告書膨大すぎ。
抄訳してもらったものをさらに人力で要約すると。
山伏は日本独自の山岳信仰を基盤とし、仏教、神道、陰陽道などが融合した修験道を実践するものたち。山に伏して修業する者たちのこと。
修業で得られた験力によって人々の現生利益に貢献してきた。
開祖は7世紀の呪術者、役小角とされるが、13世紀鎌倉時代以降には修験道が体系化され、寺院社会の「下層集団」として位置づけられると同時にその活動が社会的に認知されてきた。これによって山伏グループは既存の権力構造に適応し、制度化され、成長してきた。
室町時代から戦国時代にかけては、天台宗系の「本山派」と真言宗系の「当山派」という二大派閥に組織化され、武家社会や権力者をパトロンとして軍事面、経済面での影響力を持つようになり、またその機動性と情報伝達能力から間諜としての機能も有するようになった。
一方、月山、羽黒山、湯殿山の出羽三山をその活動拠点とする羽黒山伏は主要な教派から独立し、北前船と豊かな土地を背景として裕福な庄内地方の人々のための、豊作や現生利益を祈願することで独自の位置づけを獲得してきた。その檀家(あるいは檀那、霞などとも言われたらしい。要するにパトロン?)は庄内の裕福な農家や庶民であったろう。
羽黒山伏は武家社会との関係性よりも、里におりて地域守護、葬儀や供養、病気災厄からの救済などで民衆に貢献。里におりた修験者は有髪妻帯の俗的生活を送りながら兼業山伏などにもなっていく。
そして妻帯を許されたからこそ、その血脈は出羽地方の羽黒山伏のみが今も継承され、その子孫が山伏として生きているらしい。
Google AI の情報ソースとなったURLがリストアップされていたので、拾い読みしていくと、面白いサイトを見つけた。
庄内観光サイトの「観光の舞台裏Vol.7 山伏/出羽三山宿坊 養清坊 当主 星野博」という記事だ。
羽黒町で400年以上宿坊を営む星野家に生まれた当主は、山伏としてそれを継ぐものとして育った。紆余曲折を経て彼は「出羽三山の魅力を多くの人に伝えたい」と切望するようになる。
山を鼓舞する目的のために作ったグループはやがて400人ものボランティアを迎え、荒廃した寺を復元、整備したり、かつて多くの月山詣での人々でにぎわった山小屋を復元するなどの活動をはじめた。
そんななかで山伏修業のすばらしさも訴える。
文化を絶やしてはいけないと、星野氏自身が協会長を務める、羽黒町観光協会で山伏修業体験塾なども手掛けている。
アルファベットで「Shugendo」というワードをGoogle検索すると、Wikipediaにつづいてまっさきに羽黒町による山伏トレーニングの案内サイトがヒットする。
こういった資料類を読むにつけ、山伏修業体験を呼びかける側も、それに感応して参加する側にも本気度を感じてきた。
山伏体験塾は外国人ツーリストに特化した観光アミューズメントなどではなく、修験道の文化に感応した人に等しく与えられた機会であり、実際日本人も予約がなかなかとれないほどの盛況ぶりが伺える。
今や山岳信仰という、今は特に根源的な重要性を持つ文化に、日本人よりも海外の人たちがより深く共鳴して、熱心に参加機会を探っているのかな~と、居住まいを正す必要を感じた次第。
月山は想像通りものすごく素敵な山だった。でも有名登山ルートゆえの俗っぽさを感じて、月山周辺はもうこれでいいかな・・・と思っていたのだが、出羽三山もコンプリートしなければかな~?
